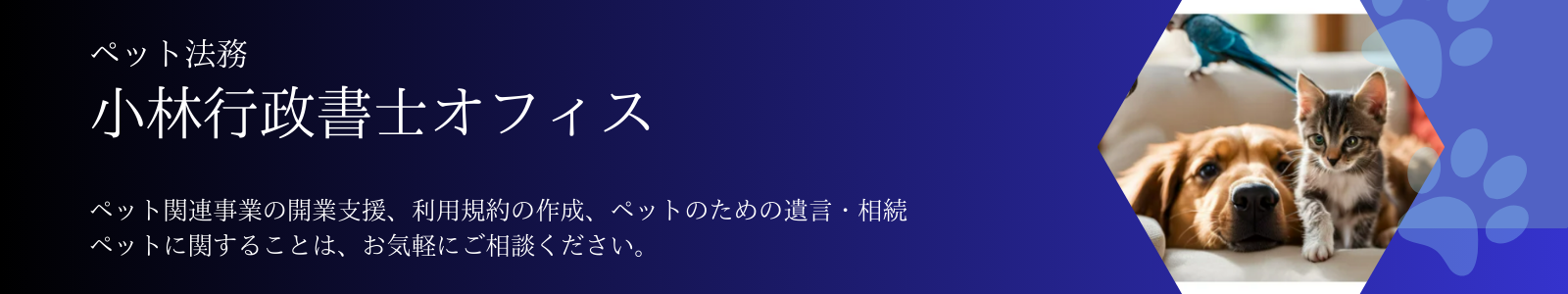ペットのための遺言書 ― 大切な命を守るためにできること
「もしも自分に何かあったら、この子はどうなるのだろう…」
ペットと暮らす方であれば、一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
ペットは法律上「物」として扱われます。そのため、遺言書の中で「所有物をどうするか」という形で将来を託すことが可能です。
今回は、ペットのために遺言書を残す方法についてご紹介します。
遺言書とは?
遺言書は、「自分が亡くなった後、財産や想いをどう託すのか」を示すための書面です。
口約束だけで十分な場合もありますが、トラブルを防ぐためには法的効力のある遺言書が有効です。
「遺言書があればよかったのに…」と後悔しないために、事前に備えておくことが大切です。
参考記事⇒ ペットのための信託・後見とは ― 大切な家族を守る選択肢
ペットのための遺言書の考え方
例として、飼い主Aさんと愛猫「たまちゃん」のケースを考えてみましょう。
Aさんが遺言書に「私が亡くなったら、たまちゃんを長男Bに引き取ってほしい」と書いた場合、
所有権は移りますが、実際に世話をしてくれる保証はありません。
また、ペットの飼育には餌代や医療費など多くの費用がかかります。
そのため、財産とお世話のお願いをセットにして記載することが大切になります。
「負担付遺贈」という方法
遺言の方法のひとつに、負担付遺贈(ふたんつきいぞう)があります。
これは「ペットのお世話をすること」を条件に、財産を渡すという仕組みです。
ただし、もらった財産以上の負担は義務づけられません。
例えば50万円を渡しても、長期的な治療や飼育で100万円以上かかる場合、飼育放棄につながるリスクもあります。
そのため、遺言書を書く前に事前に十分な話し合いをしておくことが重要です。
遺言書を書く前に確認しておくこと
- ペットのお世話を本当に引き受けてもらえるか承諾を得る
- 散歩や食事、持病がある場合の治療や薬のこと
- 死後の供養について
- 金銭面の取り決め
- その他の希望
さらに、遺言書には「付言事項」として法的効力のない想いを添えることもできます。
遺留分に注意
遺言でペットのために財産を多く残したい場合でも、他の相続人(配偶者や子どもなど)には「遺留分」という最低限の取り分があります。
全財産をペットのためだけに残そうとすると、トラブルになる可能性があるため注意が必要です。
遺言書の種類
- 公正証書遺言:公証役場で作成。費用はかかるが確実性が高い
- 自筆証書遺言+法務局保管制度:費用も安く、裁判所での検認不要で、保管も安心
- 自筆遺言(自宅保管):費用はかからないが、裁判所での手続きが必要
最近では、法的効力はないものの「エンディングノート」で想いを残す方も増えています。
遺言執行者を決める重要性
遺言書を実現するためには、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
- 預貯金の解約手続きなどを単独で行える
- ペットのお世話がされているかをチェックできる
- 義務が果たされない場合、家庭裁判所に「取消し」を請求できる
遺言執行者は未成年者や破産者以外であれば誰でもなれますが、安心のために専門家へ依頼するのが望ましいです。
遺言書以外の方法
遺言書に不安がある場合は、契約で備える方法もあります。
- 負担付死因贈与契約
- 負担付生前贈与契約
- ペット信託
- ペット後見制度
より確実にペットの将来を守る手段として、こうした選択肢を検討することも大切です。
まとめ
遺言書は、ペットの未来を守るための有効な手段です。
ただし、一方的に書くだけでなく、事前の話し合いとバランスの取れた相続設計が不可欠です。
大切なペットが一生安心して暮らせるように、
- 遺言書を準備する
- 遺言執行者を指定する
- 必要に応じて契約や専門家に相談する
こうした備えをしておくことが、飼い主としての責任のひとつになるのではないでしょうか。
ペットのための遺言書について、当オフィスにお気軽にご相談ください。