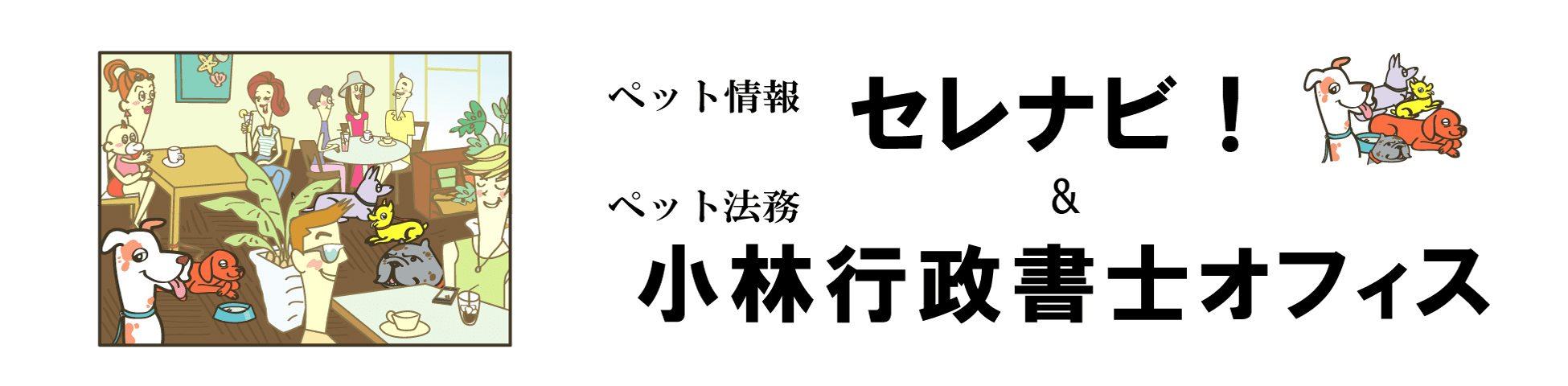ドッグカフェ【ペットと同伴できる飲食店】を開業する際には、少し複雑な衛生基準が存在します。
自治体によって定められている内容が少し異なりますので、今回は、名古屋市での手続きを参考にしてご紹介させて頂きます。
ドッグカフェとは
法律的には、ドッグカフェという定義は定まっておらず、
犬連れで入店して飲食ができるお店 = 『いわゆるドッグカフェ』と言われています。
いわゆるドッグカフェを開業する際は、飲食店の営業許可で開業できますが、
抜け毛や汚物等が考えられるということで、人に対する衛生配慮が必要なため、一般的な飲食店の許可申請と同時に、調理場と客席の区画や、客先に手洗い場の設置などいくつかの条件が追加されます。
テラスのみ犬連れOKの場合は、通常の飲食店の営業許可で営業することができます。
関連記事 ⇒ 【動物取扱責任者】とは?ペットビジネス開業に必要な3つの要件とは?
①飲食店営業の営業許可を所轄保健所に申請する
通常の飲食店の営業許可を申請する際と同じ申請ですが、いわゆるドッグカフェとして、更に営業施設の基準があるため、事前に確認が必要です。
保健所での飲食店営業許可を申請する際に、「ドッグカフェ」とすることを記載し、規定に沿った準備をすること
・厨房とイートインスペースに、しっかりとした区切りがあること
犬の抜け毛などが調理スペースに入らないように、調理スペースと客席の間に、壁や扉や窓などをつけて完全に区切ることが必要です。
調理しながら、お客さんと会話ができるようなオープンキッチンでは、犬を入店させることはできません。
・犬用メニューの提供や犬用食器を使う場合は、人用とは別に、もうひとつ水回り・調理設備が必要
犬用と提示したメニューを調理提供する場合や、食器を使用して犬に水や食事を提供する際には、人用と同じ調理場を使用することはできません。※犬用メニューとすることで、調理場の用途が変わり、人用飲食店営業許可の衛生基準が満たされなくなります。
調理場2ヶ所の設置ができないときは、1つの方法として、「犬用」と提示するのではなく、「人も犬も食べられるメニュー」として提供し、使い捨ての容器(紙皿やプラスチック容器など)を使用し、使用したものを毎回破棄します。※人用に販売されている食材を使用する場合のみ
●厨房を2か所設置し、犬用メニューのイートイン提供にはペットフード製造事業者としての届出は不要ですが、テイクアウト販売を行う際には届出が必要です。
●厨房1ヵ所で、人も犬も食べられるメニューとしてイートインでの提供には、飲食店営業のみで行うことはできますが、ケーキなどのテイクアウト販売する際には、菓子製造業としての許可が必要です。
テラス席だけで、水を提供する際にも、犬が使用した皿を厨房内に持ち込んだりすることは出来ないので、使い捨てを容器を使用したり、屋外などで洗える環境を整えておくことが必要です。
・市販されている犬用フードを調理、盛付け等する場合は、厨房が2つ必要
上記で記載のとおり、人用に売られているもの、(例えば、にんじん、さつまいも、卵、小麦粉、など)から、人も犬も食べられるメニューとしておやつや食事を調理する場合には、人用と同じ調理場を使用することができますが、
犬用(犬用ジャーキー、犬用ハンバーグ、犬用雑炊など)と販売されているものは、人用の調理場で開封して調理、盛り付けなどができません。
仕入れをした犬用のフードを提供する際には、厨房を別々にするか、客席で未開封のものを使い捨て容器と一緒にお客様に提供し、人用の食器を絶対に使用しないことを伝え、お客様自身で開封して犬に与えて頂くことで提供が可能になります。
・客席にも、手洗い場を設置
犬が店内で排泄をしてしまった、嘔吐をしてしまったなどといった場合に、処理をしてからすぐに手が洗える場所を、客席にも作っておく必要があります。
手洗い場の設置場所が重要になるため、店内の見取り図と一緒に保健所での確認が必要です。
・店内に、犬用のトイレスペースはつくれません
「トイレ(排泄)を済ませてから入店してください」とご案内をします。(実際にはどこで済ませたらよいのか、お店側からは曖昧な表現しかできません。)
近隣とのトラブルを避けるため、排泄ができそうな場所を誘導する事も控えるよう、保健所からの指示もあります。
どこでトイレを済ませて頂くのかは、お客様の判断になる為、お店側は、近隣とのトラブルに発展しないよう、掃除等の配慮も必要です。
また、衛生面を考慮して、店内でのトイレシートなどの使用は、お客様にもお断りをします。
関連記事⇒ 犬と入店できる飲食店でのマナーとは?【基本的なドッグカフェマナー10ヵ条】
②食品衛生責任者の設置の義務
通常の飲食店営業と同様に、自治体の条例に基づき、営業者には、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
食品衛生に関する講習会の受講が必要になりますので、営業施設のある保健所窓口にて確認をします。
栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者などの資格がある方は、有資格者として受講内容が免除されます。
③犬用のご飯やおやつをテイクアウト販売するには、農林水産省への届出が必要になります。
犬用ご飯やおやつをテイクアウト用に調理販売する際は、ペットフード安全法による農林水産省への届出が必要です。
関連記事⇒ 犬猫用のご飯やおやつを作って販売するために必要な資格や手続き【ペットフード安全法】とは?
④看板犬をおくためには、第一種動物取扱業の登録が必要
『動物の愛護及び管理に関する法律』に基づき、犬を看板犬としておいて営業する場合には、展示業に該当し、動物取扱責任者として、第一種動物取扱業の登録と研修などが必要です。
関連記事⇒ 『動物愛護法』とは?動物の愛護及び管理に関する法律をわかりやすく解説!
⇒ 動物取扱責任者とは?ペットビジネス開業に必要な最初の3つの要件
⑤開業届などの書類を所轄の税務署に提出
所管の税務署に、「個人事業の開業届」や青色申告の際は、「所得税の青色申告申告承認書」などを提出します。
白色申告からも可能ですが、できれば青色申告からスタートしていくことをお勧めします。
⑥防火管理者の設置や『防火対象物使用開始届出』について、事前に所轄の消防署に確認
店舗の収容人数が営業者を含み、30人以上になる営業施設では、防火管理者の設置や届出が必要です。
小規模スペースでも、事前に消防署に確認をしておいた方がよいでしょう。
関連記事⇒ 収容人員30人以上の飲食店や物販店舗などの開業時に必要な【防火管理者】とは?
まとめ
ドッグカフェを開業する際に、必要な資格はありませんが、ドッグカフェとしての衛生面を考慮した飲食店営業の許可が必要です。
お店の内装工事を始める前に、営業施設の基準に合うよう、事前に保健所に確認をとることが大切です。
事業内容によって、看板犬を置くのか、犬用のご飯やおやつの調理やテイクアウトサービスも行うのか、などによっても必要な手続きが追加されます。
スムーズかつ安全に事業を行うために、少しでも参考にして頂けたら幸いです。
関連記事⇒ ドッグカフェを開業する際に、考えておきたい5つの注意点
~これから、ペットのお仕事をはじめようと考えている方へ~
著書『ペットビジネスフィロソフィ』